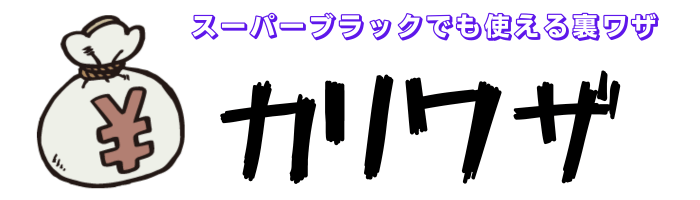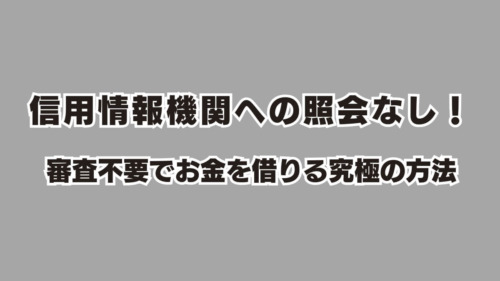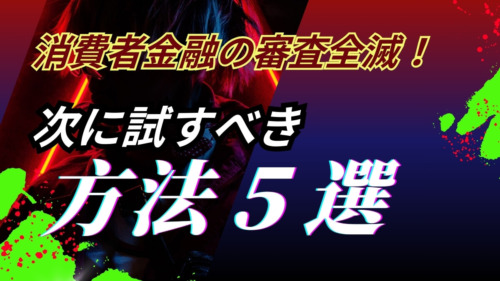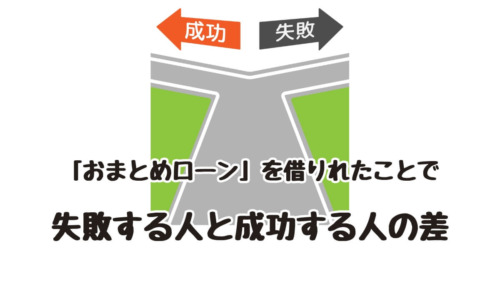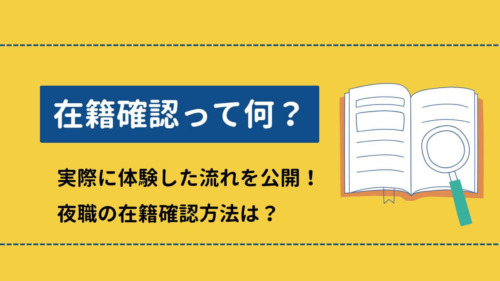サラリーマンや主婦が起業を考える際、成功の鍵となるのは事前の準備と正しい知識です。
資金調達の方法や税務・法務の手続き、副業との兼ね合いなど、知っておくべきポイントは多岐にわたります。
特に、開業資金の確保には融資や助成金の活用が重要であり、事業計画の策定が成功の第一歩となります。
最近では、クラウドファンディングを活用される方も多くなりました。
また、扶養の範囲や社会保険の影響を理解し、収入の変化に備えることも欠かせません。
本記事では、起業をスムーズに進めるための具体的なステップや、サラリーマンや主婦が安心して事業をスタートできるような情報を提供します。
サラリーマンや主婦が起業を考える理由とメリット
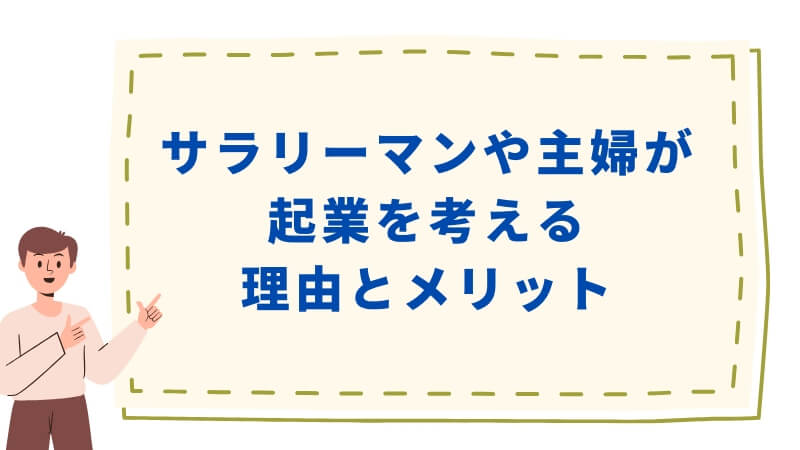
働き方の自由と収入源の多様化
近年、サラリーマンや主婦が起業を考える背景には「働き方の自由」が大きな理由として挙げられます。
企業に依存する働き方から抜け出し、自分のスケジュールで仕事ができる環境を求める人が増えています。
また、起業によって収入源を多様化させることで、一つの収入に頼らない安心感を得ることができます。
特に副業で稼げるようになれば、本業に影響を与えずに起業準備を進めることが可能です。
こうした柔軟性は新しい時代の働き方として注目されています。
副業からのスタートでリスク軽減
サラリーマンや主婦が起業に挑戦する際、副業からスタートするのは非常に賢明な選択です。
副業で事業を始めることで、大きな資金や大胆なリスクを負うことなく、事業アイデアの実現可能性や成功の可能性を試すことができます。
また、副業として始めれば、万が一失敗しても日常生活に大きな影響を与えることはありません。
多くの成功者が実践しているように、副業を通じて試行錯誤を重ねることで、スキルやノウハウを徐々に蓄積し、着実にステップアップしていけます。
スキルアップとキャリア形成の相乗効果
起業を目指して副業を始めることは、単なる収入を得る手段にとどまらず、自身のスキルアップにも繋がります。
例えばマーケティングや商品開発のスキル、コミュニケーション能力などを実践を通じて習得することができます。
このように副業を通じて得たスキルは、本業にも活かせるため、キャリア形成においても相乗効果を生み出します。
さらに、経験を積むことで自信を深め、将来的に独立する際の大きな武器となります。
このプロセスは、サラリーマンや主婦が起業を成功させるための要となるでしょう。
起業に向いている人はどんな人なのか?
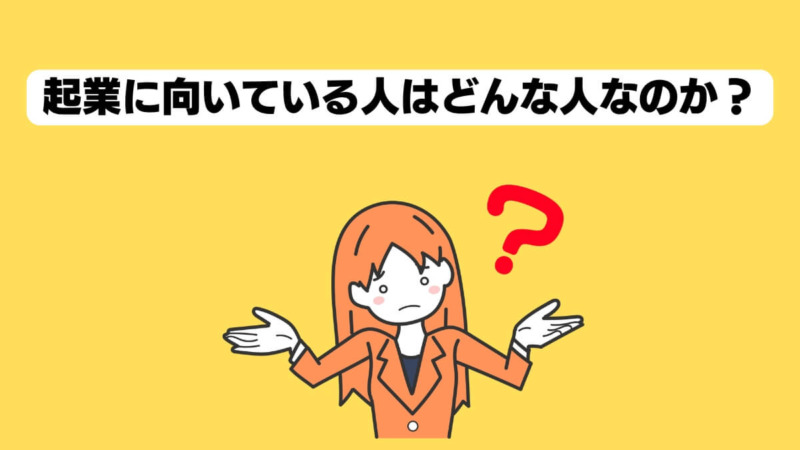
脱サラリーマンをして、起業をしようと考えている人、専門学校を卒業して、起業をしようと考えている人もいるかと思います。
しかし、起業はリスクが高いとも言われていて、失敗をしてしまった時の末路が気になってしまう・・・という人も多いですよね。
将来起業したいと考えている人は、まず自分が起業に向いているのか、向いていないのかを知ることが大切です。
そこで、起業に向いている人はどんな人なのでしょうか。
- 思い立ったら行動する人
- ノウハウを持っている人
- 柔軟な人
- 本質を理解できている人
- マーケティングができる人
- 決断力のある人
- 人脈がある人
- ストレス耐性がある人
など、様々な要素があります。
どれか一つでも欠けていたら、突き抜けるには難しいかもしれません。
今は持っていない、自分はそんな人じゃないから起業に向いていないのではないか?
と思い込んでしまっている人もいるかと思います。
ですが、そういう人じゃなくても努力次第では、自分を変えることが出来るのです。
ですから、起業に向いていない人だからといって、諦めてしまうのは勿体ないです。
そこで、自分が起業に向いているのか、向いていないのかを判断するためにはどうやって知れば良いのでしょうか。
起業に向いているのかのテストがある!?
実は、自分が起業をする人物に相応しいか、そうではないのかを判断するテストが存在します。
科学的に証明された起業家タイプの診断テストになります。
シリコンバレーのスタートアップ起業家育成プログラム、「The Founder Institute」では、科学的な側面から、起業家適性テストを作成しているものもあります。
参考記事>>JETRO「始動 Next Innovator 2020(グローバル起業家育成プログラム)」、シリコンバレー・プログラム選抜メンバー20名を決定
まずはそういったテストをして、自分は起業に向いているのか、向いていないのかを知ることもできます。
こんな人は起業しないほうがいい!その理由とは?
これから事業を起こそうと考えている人や、脱サラして起業に挑戦をしようと考えている人は多いです。
新しい事業を起こして成功をすれば夢を叶えることもできますし、大金持ちになることだって出来ます。
お金だけではなく名誉も欲しいまま手にすることができます。
しかし、起業を絶対にやめておいた方が良い、という意見も多いです。
- 失敗した場合のことを考えていない
- 自分で責任を取れない
人生を台無しにする可能性もある
「起業なんてものは成功しない」(悪いこと言わないからやめとけ)
「会社なんて始めるべきではない」(失敗したら周りに大きな迷惑をかけることになるぞ)
こんな言葉を聞いたことがありませんか。起業なんて必ずしも成功するわけではないです。
現在では、起業をした人が100人いたとしたら90人が失敗しています。
その中でも多額の借金をした人は、ほとんど全員と言っても過言ではないのです。
失敗してしまった時、誰が責任を取ってくれるのでしょうか。
誰が面倒を見てくれるのでしょうか。
全て自分で責任を取らなければいけない
起業に失敗した場合、家族にも迷惑がかかります。
起業をして、失敗してしまった場合「仕方がない」と諦めてしまう人もいます。
ですが、実際にそんな事を言っていられるわけではないのです。
結婚をしている人や子供がいる場合、家族に迷惑がかかってしまうのです。
万が一、借金をしてしまった場合、自分だけではなく家族にも影響があります。
最悪の場合、子供にも迷惑がかかってしまい、子供が一生かけて、借金を返さなければいけない事にもなってしまいます。
また、従業員にも迷惑がかかります。
一生恨まれて生きていく、といっても過言ではないのです。
そんな可能性もあるのに、起業をやるべきなのなのでしょうか。
起業前に準備しておきたい重要なポイント
アイデアの選定と市場調査の方法
起業を成功させる最初のステップは、アイデアの選定と市場調査です。
サラリーマンや主婦が起業をする際には、まず自分が得意とする分野や興味のあることを元にアイデアを出すことが重要です。
好きなことをビジネスに結びつけることで、長続きする可能性が高まります。
また、いくら優れたアイデアでも市場のニーズに合っていなければ成功は困難です。
そのため、競合分析やターゲット顧客の調査を行い、具体的な市場ニーズを把握することが必要です。
オンラインアンケートやSNSを活用して意見を集めることも、低コストで効果的に市場調査を行う方法の一つです。
資金調達の選択肢と計画
起業を始めるうえで、初期資金の確保は欠かせません。
多くのサラリーマンや副業を始める主婦が失敗する理由の一つに、十分な資金計画を立てないまま事業を始めることがあります。
資金調達の方法には、自己資金の利用、融資、補助金の活用、クラウドファンディングなどさまざまな選択肢がありますが、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。
例えば、副業として少額から初めて収益を積み重ねる方法ならリスクを抑えつつ資金を確保できます。
また、銀行からの融資を受ける場合は、事業計画書をしっかり作成して信頼を得ることがポイントです。
計画的に資金繰りを行うことが稼げるビジネスの基盤を作ります。
必要なスキルの取得と活用法
起業を成功させるためには、事業の運営に本当に必要なスキルを特定し、学ぶ努力を惜しまないことが重要です。
例えば、マーケティング、会計、営業などの基礎的な知識があると、事業運営がスムーズになります。
特に、デジタル時代では、オンライン広告やSNS運用スキルが強力な武器となります。
また、スキルを学ぶ際、座学だけではなく実践を通じて経験値を積むことが大切です。
副業から始める場合、少しずつ新しいスキルを取り入れながら試し、フィードバックを活用して改善していくと、キャリア形成にもつながります。
このようにして、新たなスキルを活用し、事業の成長を目指しましょう。
サラリーマンの副業やニートの起業が個人事業主として認められるのは簡単

サラリーマンの副業でも、主婦やニートがちょっとした起業したことでも、個人事業主(フリーランス)になれば事業性資金として総量規制以上に借りれるのです。業務を始めるのであれば、きちんと開業届を提出しましょう。
新規開業の届けは税務署の窓口で屋号を決めて書類を書くだけの簡単な作業ですが、面倒な確定申告は全国にある「民主商工会(通称:民商)」に任せれば簡単に作ってくれます。
民商の料金は入会金を含んでも1万円程度ですので、今すぐにでも個人事業主になることができます。
これはあくまで税務署と自分との簡単なやりとりなので、これを提出したからと言って会社にバレることはありません。
持続化給付金だってもらえたはずです。
サラリーマンでも、開業届を出して修正申告をすれば、いつからでも個人事業主となり、確定申告書の控えが必要な借入れも可能になるわけです。
しかも初期投資がほぼ0円で個人事業主になる方法があります。
先ずは開業した(する)ことの届けを出す

開業届を提出しておくと、確定申告の時期に必要な用紙を送ってもらえます。また、青色の申請をしておけば、様々なメリットも得られますので、納税地を管轄する税務署に行き、開業届出書を提出します。
届け出に必要なものは、印鑑と筆記用具だけです。
業種は任意(実際の事業)のもので構いません(例:オンラインストア)。
開業届出書は税務署に行けばもらえますが、先に用紙に記入して行くと5分程度で終わります。
個人事業の開業・廃業等届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
青色申告にするとメリットが高いようですが、白色申告でもOKです。
起業すると総量規制以上に借りれるようになる
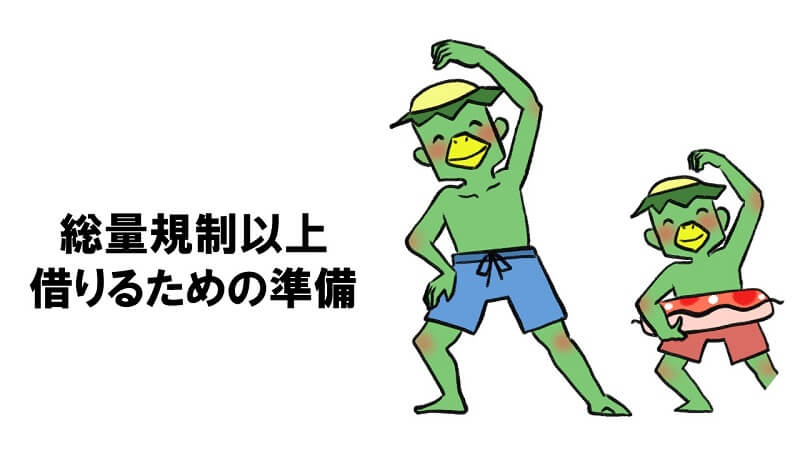
起業後に総量規制対象外のビジネスローンを借りる場合には固定電話は必要不可欠です。
自宅に固定電話がある場合には、屋号で104登録も済ませます。
もし固定電話を今から設置したいなら、初期費用0円でも固定電話が引けます。
ホームページはなくても構いませんが、あるに越したことはありません。
開業届が出されていなくても、ホームページがあることで自営業者とみなしてくれる金融機関もあります。
自分で制作できる場合は、無料レンタルサーバーや、無料体験付き格安でできるオンラインストアなど活用して下さい。
これでビジネスローンを活用する準備が整いました。
ビジネスローンの他、日本政策金融公庫で新規開業資金が借りれますし、返済の必要ない助成金をもらうこともできます。
日本政策公庫は、フランチャイズ加盟すると審査が通りやすくなります。
起業して個人事業主になった場合のメリット

サラリーマンとして給料をもらいながら個人事業主になった場合には、総量規制以上に借りれるということだけがメリットではありません。
開業の届けを出せばビジネスローンが受けられるだけでなく屋号(店名)で口座が作れたり、領収書を集めて経費として申告すれば住民税が安くなったりもします。
クレジットカード決済での販売も可能になります。
- 青色申告で65万円の特別控除
- 赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
- 家族に給料を払ったとき、経費にすることができる
- 物を買ったとき費用にできる
- 自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる
青色申告で65万円の特別控除
帳簿付けを複式簿記で行っていれば65万円を、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っていれば10万円を、課税所得から差し引くことができます。
これを青色申告特別控除といいます。
年度の途中に開業した場合でも、上記の控除額を月割りする必要はありません。
青色申告の申請が承認されていれば、65万円または10万円が全額控除できます。
ただし、青色申告特別控除前の所得金額(=収入-経費-各種引当金・準備金等)が、上記の額より少ない場合は、その所得金額=控除額となります。
例えば複式簿記で帳簿付けを行っており所得金額が55万円の場合、青色申告特別控除額も55万円となります。
赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、向こう3年以内に出る所得と差し引くことができるものです。
例えば、
2018年 500万円の赤字
2019年 300万円の赤字
2020年 100万円の赤字
2021年 1000万円の黒字
となった場合、2021年の課税所得は
1000-(500+300+100)=100万円となります。
また、前年度も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、(前年の課税所得金額-本年度の赤字額)を還付してもらうことも可能です。
家族に給料を払ったとき、経費にすることができる
事業主の家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。(※白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り課税所得から差し引かれます。)
これを「専従者給与」といい、専従者には、同居または生計を一にしている15歳以上の配偶者や親、祖父母、子供などが含まれます。
※目安として「1日6時間以上、月に15日以上ないしは、年間で6か月以上相当」の期間を、事業主の事業のために費やすことが条件で、アルバイトや日雇いとしての雇用には適用されません。
※「専従者」になった人は、所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません。
物を買ったとき費用にできる
パソコンや電話機といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。
しかし、青色申告者が10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができます。(※白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産を取得した場合にしか、一括で経費とすることができません。)
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる
青色申告の場合、自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や住宅ローン、水道光熱費、通信費等の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。
一方、青色申告の適用を受けるためには、必要書類の数や申告手続きの手間を増やさなければありません。
起業後の青色申告は面倒なのがデメリット
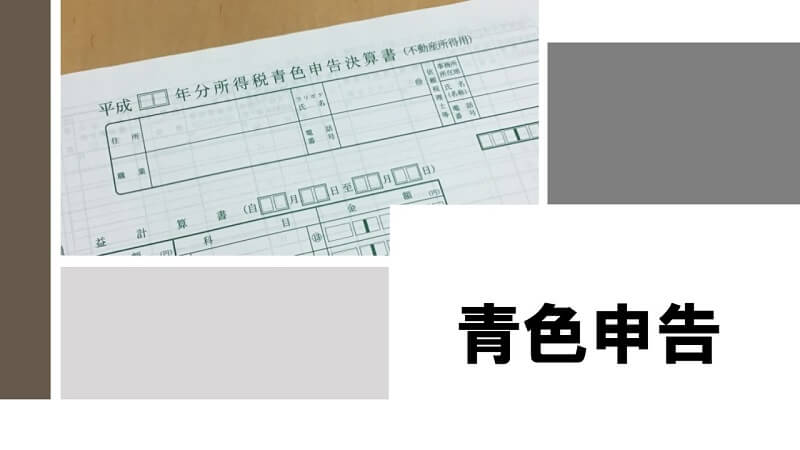
青色申告を始めたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は、同申請書を、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。
青色申告では、複式簿記での記帳をする必要があり、売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
白色申告では、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出する必要がありますが、それに比べて提出書類の数や項目が増加します。
白色申告とは、青色申告の申請を行っていない人が使用しなければならない申告制度です。
所得税の税額計算のベースとなる「課税所得」は、課税所得=(収入-必要経費+その他の所得)-各種所得控除という計算式で求められます。
また、青色申告では、帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生します。
なお、白色申告では、上記の義務(入出金等の記載は単式簿記でかまいません)が、事業所得・不動産所得・山林所得の合計が300万円を超える事業主に限り発生していましたが、2014年1月1日からは、事業所得等のあるすべての事業主に義務付けられることになりました。
青色申告を簡単にできる無料ソフト
上記の通り、フリーランスとして開業する際に青色申告を選択することで、白色申告に比べて数万円~数十万円の節税効果が期待されます。
提出が必要な書類の数や提出期限の面で負担は増えますが、今後の制度改正で白色申告との負担の差は縮小することが予想されます。
開業時には、ぜひとも青色申告をされることをおすすめします。
持続可能な起業を成功させる秘訣
事業拡大のタイミングを見極める
起業を成功させるには、事業拡大を進める適切なタイミングを見極めることが非常に重要です。
事業が安定し始めると、新たな市場への挑戦や顧客層の拡大を検討しがちですが、新しい展開には必ずリスクが伴います。
そのため、拡大を進める前に現在のビジネスの収益性や市場規模を慎重に分析し、財務的に無理がないかを確認しましょう。
また、早すぎる拡大は事業運営における混乱を引き起こし、失敗につながる可能性もあります。
「今以上にリソースを投入しても利益率が維持できるのか?」といった具体的なシミュレーションを行うことが拡大成功のカギとなります。
サラリーマンや主婦が起業をする際には自身や周囲への負荷がかからない範囲でステップを踏んで進めることが求められます。
人脈構築とパートナーシップの重要性
起業を継続的に成功させるためには、人脈構築とパートナーシップが不可欠です。
信頼できる人々とのつながりや、業界内外の専門知識を持つ人々とのネットワークは、ビジネスの可能性を広げる上で大きな力となります。
たとえば、顧客紹介をしてくれる仲間やビジネスのアドバイスをしてくれる先輩起業家がいるだけで、事業の方向性を修正したり、成長のチャンスを逃さずに済む可能性が格段に高まります。
特に、主婦が起業を考える際には、家事や育児との両立を理解してくれるパートナーや協力者を見つけることも重要です。
イベントやセミナー、SNSを活用した交流の機会を大切にし、共に成長できる関係を築いていきましょう。
人脈が広がれば、事業の拡大にも役立つ情報や必要な支援を得ることもできるでしょう。
ライフスタイルとビジネスのバランスを保つ
持続可能な起業には、ライフスタイルと事業運営のバランスを保つことも欠かせません。
特にサラリーマンが副業としてビジネスを始める際や、主婦が家庭との両立を目指す場合、時間管理が大きな課題となります。
家庭や本業、事業運営のどれか一つに偏りすぎると、それぞれに支障が出る可能性があります。
効率的なスケジュールを設定し、必要以上に労働時間を費やさず、一日の中で休息時間もしっかり確保することで、心身の健康を維持できるよう心がけましょう。
また、あらかじめ事業運営の優先順位を明確にし、「できること」と「できないこと」をきちんと見極める姿勢を持つことが成功への近道です。
適切なバランスを取ることで、稼げる仕組みを構築しながらも、ライフスタイル全体の満足度を高めることが可能となります。